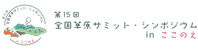開催の目的
火入れや、放牧、採草などによって維持されてきた半自然の草原や湿原は第二次世界大戦後、燃料革命などによって、価値が激減し、維持されている草原は希少となっています。明治時代は国土の20%を占めていた草原は現在では1%まで減少しています。
この希少となった草原を持つ自治体や草原に関わる全ての人々が集い、草原の価値や存在意義を全国にアピールするとともに、その自然環境や歴史的及び文化的な知識や技術を共有し、全国で取り組んでいる保全・継承活動の現状や課題について論議を深めながら、草原を維持するために連携していくことが、全国草原サミット・シンポジウムを開催する目的です。
過去の開催事例、内容
草原サミット・シンポジウムは過去14回、全国草原の里市町村連絡協議会に所属する草原を持つ自治体で開催されてきました。同連絡協議会は31の市町村で構成され、持ち回りでサミット・シンポジウムを開催しています。各大会の内容構成はほぼ同じで、シンポジウムとしては、その大会の問題提起となる研究者等による基調講演会、参加者とともに課題を深めるための分科会(3~4課題)、そして、その地域の現状を確認するための現地見学会を行っています。サミットは全国草原の里市町村連絡協議会に加入している市町村の首⾧が大会会場に集まり、課題を協議した結果をその大会の「サミット宣言」として採択します。


ここのえ(九重)大会の意義
草原は、かつて九重町全域に分布していましたが、現在でも野焼きを継続している草原は「くじゅう飯田高原の草原」(未来に残したい草原の里100選)など限られた地域になりました。野焼きを実施する地域住民の高齢化や、採草放牧地としての利用減少とともに、野焼きを行う地域が年々減少しています。また、草原の減少にともない、草原でしか生きていけない生きものの減少は著しく、多くが絶滅の危機に瀕しています。
「第15 回全国草原サミット・シンポジウムin ここのえ」では、野焼きを未来につなげていくために、九重町の草原の魅力を全国へ発信するとともに、1.一般ボランティアの野焼き参加、そのための更なる安全管理について考える大会とする 2.草原の価値と野焼きの重要性について町民の理解を深める 3.草原の植生や生物多様性の保全につなげる 4.新たな草原の価値を見出し活用について考える といった方針のもと開催します。
「野焼き文化と草原のめぐみ」を未来へつなぐためには、地域住民の力が必要不可欠です。草原は、私たちの生活とは関係ないと思っている方も多いと思いますが、実は人は、草原からさまざまな恵みを受けていて、草原と人々の暮らしはつながっているということを再認識するような大会としたいと考えています。